柳誌『水脈』が第70号をもって終刊となった。終刊号をいただいたので、読んだ感想を書く。
巻頭は、第69号から引き続いて(といっても私は第69号は読んでいないのだが)、「水脈終刊にあたって――70号を振り返る②」と題し、第31号からの歴史が綴られる。筆者は浪越靖政さん。同人の入れ替わり、運営陣の交替、作品評の執筆者紹介、「創連」・「いちご摘み川柳」の歴史と一部の紹介、「一句にふれて」の歴史と一部の紹介、イメージ吟の歴史と一部の紹介、毎回柳誌発行後に開催されていた合評会のこと、同人の皆様が刊行された句集について、そして、「おわりに」の言葉で締めくくられる。第一号が発行された2002年4月からの23年間の重みが、全7頁の中に詰まっている。私はついに『水脈』に加わることはなかったが、同人の方々の幾人かとは様々な形で面識があり、終刊を惜しむ気持ちに共感する。ただ、幕引きの決断が希望も含んでのことであるのが救いである。
9頁からは、同人の作品10句ずつとエッセイを掲載。印象に残った句を引く。
水脈完結 ギッチョンチョンなり 佐々木 久枝
「ギッチョンチョン」に「東京節」のサビを思い浮かべる。水脈の終刊は寂しいけれども、せめて賑やかにそれを迎えたい、という気持ちだろうか。
チーズフォンデュ具材はあぶない言葉 澤野 優美子
たっぷりとチーズを絡めたら、あぶない言葉もするりと相手に飲み込ませることが出来そう。惹かれるけれども怖い句だと感じる。
千年も経てばまたぞろ詩を書きに 一戸 涼子
千年の長さに私などは気が遠くなるが、こう軽やかに書かれると案外短いのかも?と思ってしまう単細胞。千年後、お互い人間に輪廻転生していたら、また作者の詩が読みたい。
約束やぶるのに死はいい口実 西山 奈津実
この「死」は主体本人の「死」と読んだ。死んでまでやぶりたい約束ってなんだろう、と思うが、案外小さなことだったりしそう。
漆乾く間の白旗にアイロン 四ツ星 いずみ
思わず調べてしまったのだが、漆が乾くまでには、一般的に数時間から一、二日、時には半年から一年ほども掛かるらしい。その間主体は白旗を揚げるようだが、誰に? 何故? と想像が膨らむ。しかし、アイロンを掛けて、何なら糊付けまでしていそうなこの白旗、ちゃんとなびくのだろうか?
紙と鉛筆感情の縺れを解いていくように 酒井 麗水
書きながら、自身の感情の縺れを解く……川柳はそれに非常に向いている文芸だと思う。共感句。
完パケの慣性系が崩せない 河野 潤々
完パケとは「『完全パッケージ』の略で、映像や音声が完全に編集・加工され、放送や配信にそのまま使える状態に仕上がった完成品のこと」(Google検索、AIによる概要より)だそうだ。慣性系は、「完成形」からずらしたのかな?、と思うが、完パケの作品世界には確かに独自の慣性系がありそうで、取り込まれたら内側からは崩せないだろう。
音楽は魔物ゆるやかに開かれて 平井 詔子
自分がゆるやかに開かれ、内面をさらされてしまう、そんな音楽は確かに魔物。この句を書いた時に作者の中を流れていた曲が何なのか、知りたいような、知るのが怖いような。
見切ったら襲ってくる茶室 宇佐美 慎一
動き?設え?を見切った、と思ったら突然襲ってくる茶室。怖い。本来茶室は客人をもてなすための場で、刀も持って入れないよう躙り口から入室する。だが、貴人口という立って入れるサイズの入口が設けられている場合もあるし、戦国時代の茶室は、それこそ命のやりとりをするような緊張の場面もあったようだ。とすれば、茶室が怖いものなのもうなずける話かもしれない。ちなみに連想するのは、一畳台目くらいの小さな茶室である。
らすとダンスはやっぱマツケンサンバ 坪井 政由
十句がそれぞれ「ら、り、る、れ、ろ、わ、ゐ、ゑ、を、ん」から始まる仕掛けの一句目。『水脈』のフィナーレを飾るラストダンスには、やはりマツケンサンバがふさわしい。
引き算は心細くて寂しいね きりん
深読みかもしれないが、作者の生活から『水脈』が引き算される、ということかな、と読んだ。でも川柳も言ってみれば引き算の文芸、今は寂しくても、川柳を続けている限りきっとまた寂しくなくなる日がくると信じたい。
まだかまだかとジプシーのタンバリン 落合 魯忠
実はもう少しでロマの人々の村を訪れられる、という機会が昔あったのだが、迎えに来てくれた村の男性たちが途中で知り合いに会って酒盛りを始めてしまったため、道端の軽トラの荷台で夜を明かすことになり、村には行き損ねた。その時に聴けたかもしれないタンバリンを、いま想像の中で聴いている。そして身体は今にも踊り出しそうになる。
やっかいなやつが右脳に棲みついた 浪越 靖政
右脳の働きは、イメージによる情報処理や創造的な活動、空間認識などらしい。対して左脳は、言語能力、計算、分析、論理的思考などを司るという。左脳なら何とか論理で「やっかいなやつ」を追い出せそうな気がするが、右脳に居座られたらお手上げ。共存するか、相手が出ていく気になるのを待つしかなさそうだ。
22頁は、一戸涼子さんによる「出発点としての終刊」というエッセイ。「私は健康の許す限り文芸好き活字好きとして、心赴くまま読むほうに専念するつもりだ。」との一文に、エールを送りたくなる。
23頁からは野沢省吾氏による作品評。これはもうぜひ、何とかして実際に読んでいただきたい。
27頁からはイメージ吟。『水脈』最後のイメージ吟の選者は河野潤々さん。軒下にうずたかく積もった落雪と垂れ下がる氷柱の写真から、軽やかに発想を飛躍させた句が選ばれている。特選句は【濡れた袖のまま見つめてる卒業/クイスケ】
29頁からは、「創連(先行する川柳の言葉か句意またはイメージから作句し、次へとつないでいく)」。「男まえ(潤々、政由、きりん)」「朝にする(久枝、涼子)」「水鳥に(いずみ、慎一、優美子)」「尖ろうぜ(麗水、魯忠、奈津実)」「川柳三昧さ(詔子、靖政)」の五つの創連は、一人ではないからこそ生み出せる作品たち。最後の「川柳三昧さ」の挙句は【月月火水木金金 川柳三昧さ/靖政】・・・詠みたい/読みたい時にしか川柳を読み書きしない私は頭が下がるばかりだが、楽しそうなご様子にこちらも嬉しくなる。いつまでもご健吟を!
34頁は、澤野優美子さんのエッセイ「18cmのせせらぎ」。タイトルの「18cm」は、『水脈』第1号から第70号までを重ねた時の厚さ(想定)だそうだ。筆者と『水脈』との三年間の歴史が刻まれた美しい文。
35頁からは、浪越靖政さんによる作品鑑賞。同人ひとりひとりへの愛がこもった観賞文は必読。
38頁下段には、令和七年度(第二十一回)北海道川柳連盟賞大賞を受賞された宇佐美慎一さんの受賞作の一部が掲載されている。中から好きな句を幾つか引く。
安らぎの夕暮れはなく昼と夜
ジャンク品ひとり笑いも三年目
モビールの触れて欲しくはないところ
終電車みんな孤島の顔をして
慎一さん、おめでとうございます!
39頁からは「封筒回し・・・令和7年4月12日の合評会から」。河野潤々さんによる報告で、何とも楽しそうな様子が伝わってくる。即吟は苦手だが、一回くらいは封筒回しをやってみたくなる。
43頁下段には、「川柳アンジェリカ」さんが出されたアンソロジー『ア・ラ・カルト』より12句が掲載されている。
44頁は宇佐美慎一さんによるエッセイ「男はつらいよ」。最終節があまりにも素敵なので、ご紹介する。
「寅さんはいつもふらっと現れてはひと騒動を起こし、時に誰にも告げずにまたふらっと旅に出る。気が向いたら帰ってくるので「別れ」ではなく文章で言えば句読点ほどの意味なのだろう。「水脈」が終わるのもひとつの句読点。メンバーは各自改行や改ページをしながら新しい旅に出ることだろう。」
45頁は、きりんさんによるエッセイ「約束は…」。彫刻家の圀松明日香氏との思い出、そして水脈への想いが語られている。
46頁は「一句に触れて」。同人の皆様が、こころに触れた句への感想を綴っている。
そして最終47頁は「水源地」と奥付。「終刊号」の文字に寂しさが募るが、こうして書いてきて、全47頁とは思えぬ密度の濃さに改めて驚く。北海道に移ってから川柳を始めたのに、北海道川柳についてはほとんど知らなかった私にとって、幾冊かいただいた『水脈』のバックナンバーは、とても貴重なものとなった。深謝するとともに、この柳誌が北海道川柳のまさに水源地として、終刊後も幾つもの川を産み育てることを信じたい(文中一部敬称略)
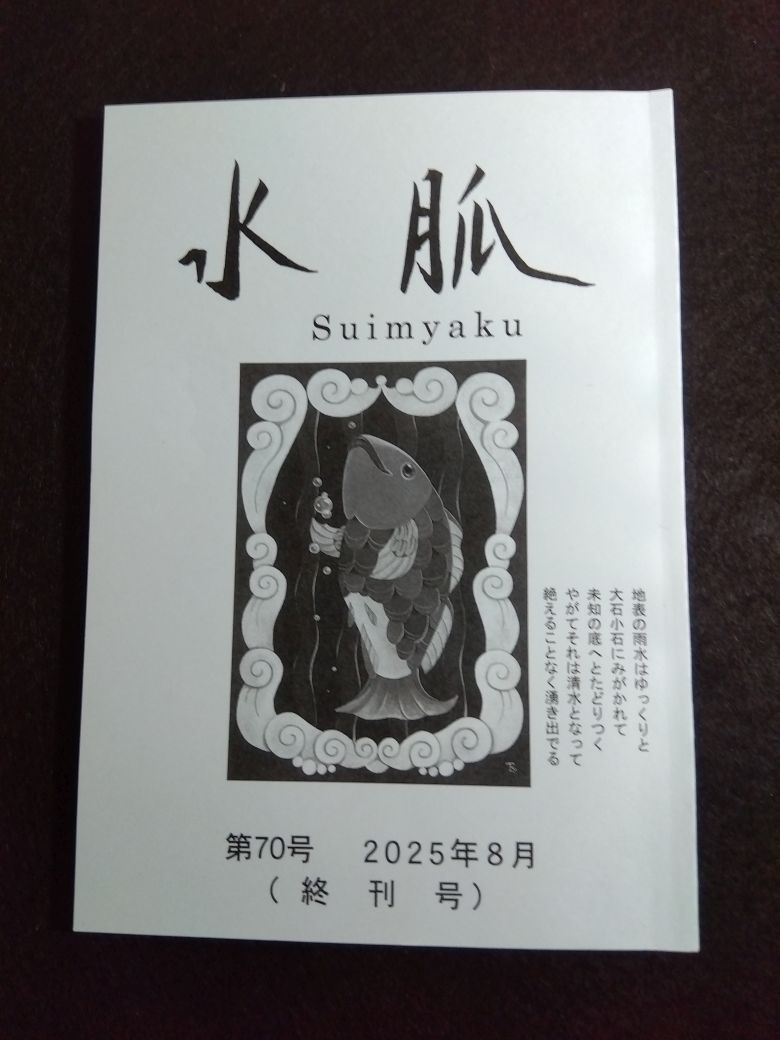

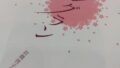
コメント